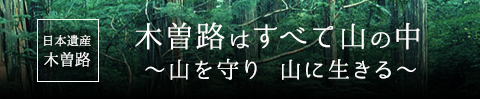
| 日本遺産木曽路 | 構成文化財一覧 |
| 木曽を語る | お知らせ |
郷土史家 澤頭 修自さん

澤頭修自さんの生まれ故郷は木祖村。十年の歳月をかけた村史編纂のかじを取り、また、木曽地域全体にも愛着と探求の目を向けてきた人だ。その素地は、各地に赴任した教師生活の中で培われてきたという。
昭和27年、人手不足の教育現場に乞われ、澤頭さんは教職の道に入った。
「はじめは腰掛けのつもりだったのが、やっているうちに面白くなってきてしまって、気づいたら42年間の教師生活でした」
そう言いながらの笑顔には充実感が漂っている。
昭和44年、開田東小学校(現開田小学校)に奥さんと幼な子を連れて赴任。マイナス20度の厳冬に震えもしたが、開田高原はそれ以上に魅力に溢れていたそうだ。

郷土史家 澤頭 修自さん
「開田の子達は皆自然児でね。山へ行くにも川で遊ぶにも私なんかより達人で、屋内より屋外で学ぶことがたくさんありました。なによりその大自然が素晴らしいから、天国へ上ったような幸せな5年間でした。」
多くの児童文学を世に遺した庄野英二氏との親交もこの開田赴任で生まれた。
「人との繋がりは大事だなあと思いますね。」
しみじみ振り返り辿る記憶の中にいるのは、庄野氏と同様、かつて懇意にしてもらったという英文学者の菊池重三郎氏だ。菊池氏は晩年の島崎藤村と交流があり、馬籠の藤村記念館の設立にも尽力した人だ。澤頭さんが南木曽町の妻籠小学校に赴任していた頃、偶然出会い、以後可愛がってもらったそうだ。1962年に菊池氏が出版した『木曽路の旅 自然と人と』は、木曽路ガイドブックの先駆け的一冊。実はその旅に澤頭さんもカメラを持って同行し、掲載写真のいくつかは澤頭さんがフィルムに収めたものだった。澤頭さんが写した貴重な木曽の風景はご本人の著作にも多く収められている。
「教員時代、木曽教育会の郷土研究会に入っていました。子ども達に故郷の大切さを教えなきゃいけないという志が皆にあって、県下でも木曽はその思いが強い土地だったと思いますよ。」
その志がこれまでの澤頭さんに軸としてあったに違いない。村史の編纂は、生まれ故郷を改めて発見する機会にもなったそうだ。

味噌川ダムにて

「幻の花」ミソガワソウ
木曽川の最上流部にある味噌川ダム。
「このさらに上流でミソガワソウを見つけたのも、忘れられないですよ。」
江戸時代より草本学者らにより存在は知られていたものの、その姿が長く確認されていなかった「幻の花」を、自然同好会の仲間と共に平成7年に見つけた。
唯一村の名前を冠した植物は、間違いなく村の子ども達に手渡していける遺産だ。
人の記憶は不確かだ。だから、書き遺す。写し遺す。
澤頭さんは今、その遺産を手渡す次の世代の若者と繋がりたいと願っている。

| ||||
|